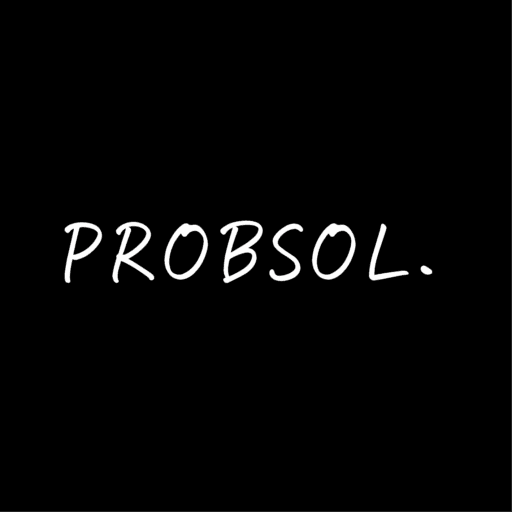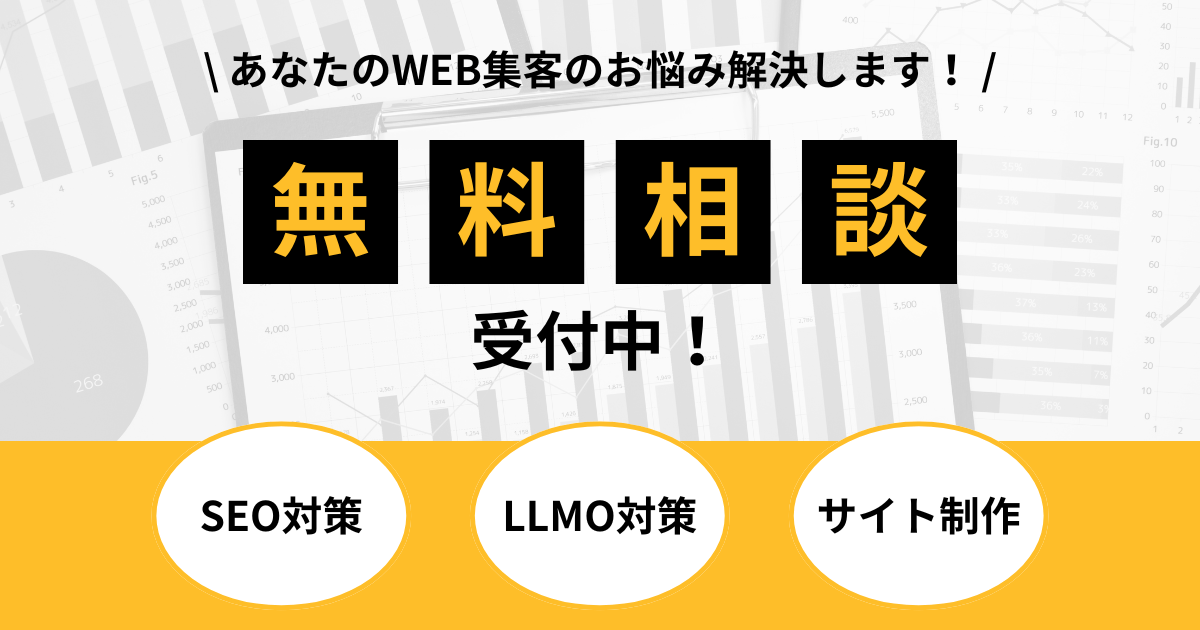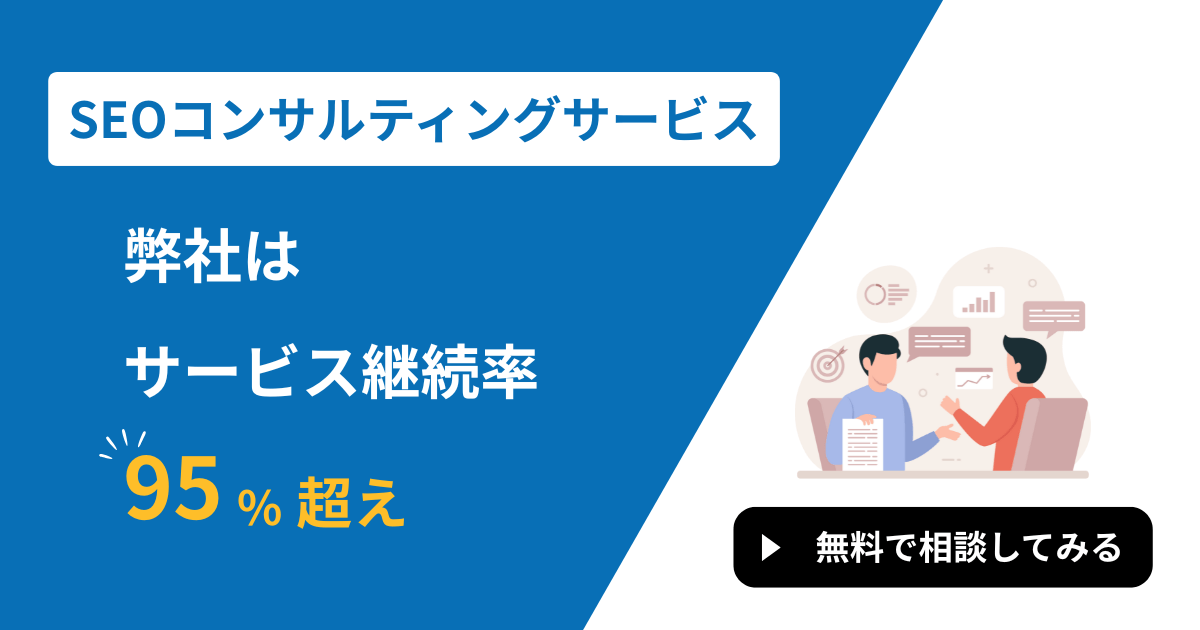LLMO対策とは?SEOとの違いやAI時代を勝ち抜くための戦略を徹底解説
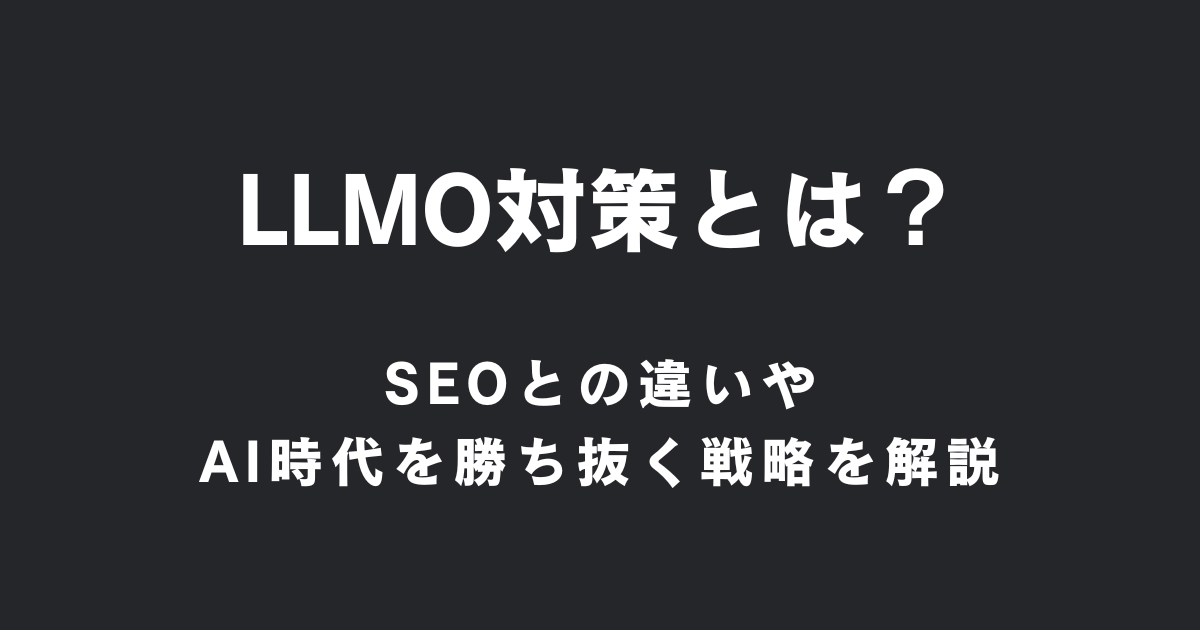
- そもそもLLMO対策って何?
- なぜLLMO対策が重要なのか
- LLMO対策では何をすれば良いか
近年、私たちの情報検索体験が根本的に変化しています。
ChatGPTをはじめとしたAIの爆発的普及などにより、従来の検索の流れから「検索→AIが直接回答を生成」という新しいパターンが主流になりつつあるのを感じている人も多いのではないでしょうか。
この変化は、Webマーケティングの世界に大きなインパクトをもたらしています。
いくら優良なコンテンツを作成し、SEO対策を徹底しても、ユーザーがAI検索で満足して自社サイトに流入しない「ゼロクリック検索」が増加すれば、従来のマーケティング戦略は効果を失ってしまう可能性があるためです。
そこで注目を集めているのがLLMO(Large Language Model Optimization)—生成AIに対する最適化を行うマーケティング手法。
LLMOは、AI検索エンジンやチャットボットが生成する回答の中で、自社の情報が適切に引用・紹介されることを目的とした最適化戦略です。
本記事では、AI検索時代に企業が競争優位を築くために必要不可欠となるLLMO対策について、その定義から具体的な実践方法、成功事例、そして今後の展望まで包括的に解説していきます。
早期に対策を取ることによって、これからの時代の変化の波に乗り遅れることなく、新たな顧客接点を獲得していきましょう。
- LLMOとは何か、SEOとどう違うか
- LLMO対策の重要性
- LLMO対策の基本戦略と実践方法
- LLMOの今後の展望
株式会社PROBSOLでは、それぞれの企業に応じた最適なLLMO対策をご提案しています。
これからLLMO対策に取り組んでいきたい方は、お気軽にご相談ください。
LLMOとは?AI時代に必須の新しいWebマーケティング
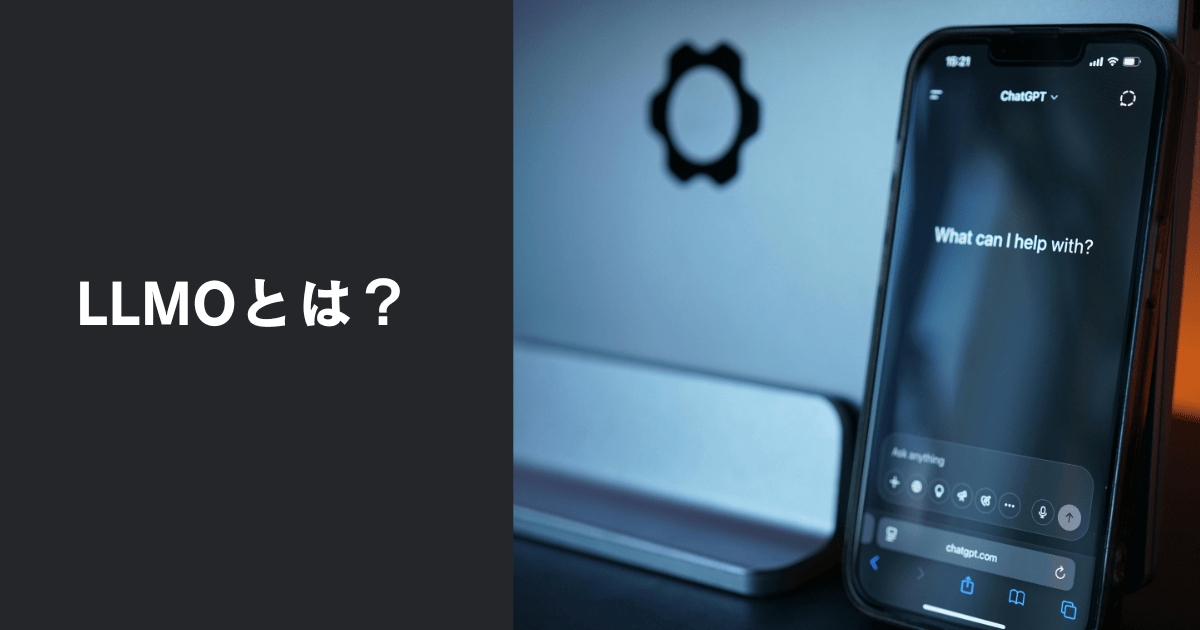
LLMO(Large Language Model Optimization)という言葉は、AI・大規模言語モデルの普及に従って登場した、比較的新しい言葉です。
そのため、まだLLMOという言葉自体に馴染みのない方も多いでしょう。
LLMOをいかにビジネスや実生活に応用していくかを考える前に、まずはLLMOが何を指し、どのような性質を持つものなのか、その全体像に関してお伝えしていきます。
LLMO(Large Language Model Optimization)の定義
LLMO(Large Language Model Optimization)とは、大規模言語モデル(LLM)に向けた情報最適化の手法のことを指します。
例えば、自社のサイトやサービスをChatGPTなどの質問への回答に組み込んでもらえるようにする対策などが分かりやすいでしょう。
従来は、GoogleやYahoo!といった検索エンジンのアルゴリズムに最適化することを目的とした検索エンジンへの最適化が主流でしたが、近年のAI技術の発展・普及により、生成AIの回答に自社の情報を組み込ませるLLMOが注目されるようになりました。
LLMOが対象とする生成AIとしては、例えば次のようなものがあります。
- ChatGPT
- Gemini
- Claude
- Perplexity
それぞれの生成AIに関する対策では異なる部分もありますが、およその方向性としてはLLMO対策として共通している部分があります。
LLMO対策は単なる検索結果に表示される順位の争いではなく、AIが提供する回答の一部として自社のサービスやブランドが引用され、ユーザーとの接点が生まれることを目指します。
結果として、次の効果が期待できます。
- 指名検索の増加
- コンバージョン(成約)率の向上
- ブランドイメージの強化
- AIの回答からの流入
イメージしやすいように、具体的な検索行動に着目してご説明します。例えば、ユーザーが「おすすめのマーケティング会社は?」とAIに尋ねたとしましょう。
このとき、AIの回答文中に自社名が登場すれば、その時に直接的なリンククリックがなくても、その場でブランド名がユーザーの記憶に刻まれます。
その結果、後日、そのユーザーが指名検索を行い自社サイトを訪れる可能性が向上。
この動きは、SEOでの「クリック獲得」とは異なる、新しい「認知経路」としての価値を持ちます。
また、Google検索で「Webマーケティング会社 おすすめ」と入力した場合にAI Overviewで自社が取り上げられ、ユーザーとの接点となるのも同様です。
ユーザーは今、ブラウザの検索窓だけでなく、AIチャットとの会話からも直接情報を得るようになっており、生成AIが出す回答文が新たな認知の経路となっています。
LLMOは単なるアクセス数の増加ではなく、AIが情報を届ける瞬間に、ブランドを想起させることにもあるのです。
こうしたAI経由の認知獲得が、今後のLLMO、デジタルマーケティングでは重要な勝負所となり、情報感度の高い企業では既に対策が進められています。
LLMOとSEOの共通点と違い
LLMOとよく比較されるものとしてSEO(Search Engine Optimization)があります。
SEOは検索エンジン最適化の略称で、検索結果で上位表示されることでより多くのユーザーにサイトを見てもらい、集客や売上アップにつなげることを主な目的としたものです。
LLMOとSEOの共通点として、例えば次のようなものが挙げられます。
- 情報の構造化
- 信頼性の担保
- 権威性の重視
検索エンジンもAIもどちらもコンピュータの働きによって機能しているため、人間だけでなくコンピュータにも理解できるように整理された「構造化データ」を好みます。
また、ユーザーにとってより良い検索体験ができるように、情報の信頼性の担保やそのための情報源となる運営者の権威性などが重視されます。
従ってLLMO対策として実施される施策の中には、SEO対策の延長であるものもあります。
一方、LLMOとSEOはその根本の目的と評価基準が異なることに注意しなければなりません。
SEOでは競合より上位に表示されることが重要ですが、LLMOではAIが「信頼できる情報源」と認識し続けることが最大のポイントです。
LLMO・生成AI最適化の具体的アプローチ
生成AIに自社情報を引用させるためには、AIが理解・加工しやすい情報構造を意識する必要があります。
代表的なLLMOの施策は以下の通りです。
- 統計データや一次情報の提示
- 簡潔かつ正確な定義文
- FAQ形式での情報整理
- 外部リンクや出典の明記
これらを体系的に整備することで、生成AIが自社サイトを積極的に引用する可能性が高まります。
具体的な対策に関しては、LLMO対策を行う企業が実際にどのようなことを行えば良いかという観点から、後ほど詳しい解説を行っていきます。
LLMOの国内外での呼び方とトレンド
LLMOに関して、海外では「Generative AI Optimization」や「AI Search Optimization」という呼び方をされることがあり、国内では「生成AI最適化」「AI検索最適化」など複数の表現が使われています。
- Generative AI Optimization
- AI Search Optimization
- 生成AI最適化
- AI検索最適化
今後も、LLMOに対応するような新しい言葉が生まれることもありますし、その使われる頻度はトレンドによって多少変化することが予想されます。
しかしながら、名称は異なっても目指すゴールは共通で、AI時代に選ばれる情報源になること。これがLLMOの最終的な目的です。
そしてそのトレンドを捉えて、重要性を認識し、対策を行っていくことが極めて大切です。
生成AIが日常の情報取得手段として浸透していく中、LLMOはSEOと同様にデジタルマーケティングの基盤として重要性を増していくでしょう。
なぜ今、LLMO対策が重要なのか
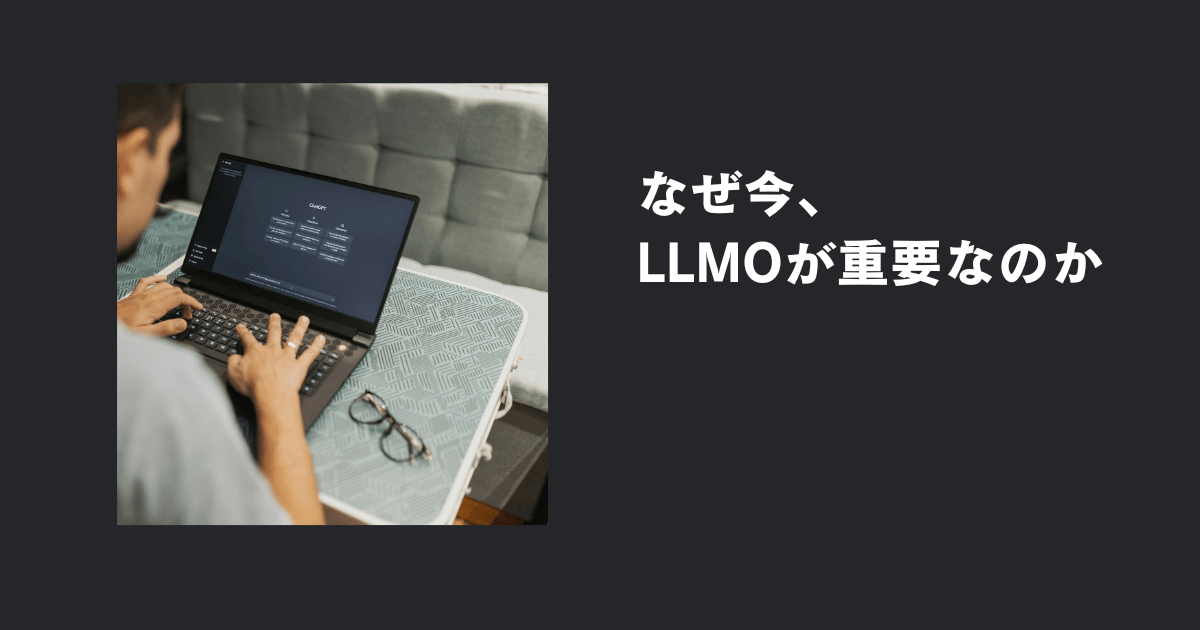
LLMOに関する全体像を把握した上で、続いては、なぜ今LLMO対策が重要なのかに関して順を追って解説します。
AIおよびLLMOに対して人々の関心が高まる中、時代に取り残されないように、最低限の背景情報を押さえておきましょう。
人々の検索行動の変化とそれに対して早急に対応することの大切さを感じることができるはずです。
検索結果から直接回答される時代の課題
スマホが登場してから人々の生活が大きく変わったように、近年、AIが普及するにつれて一般の人々の検索行動は大きく変化しています。
従来はGoogle検索でキーワードを入力し、上位に表示されたリンクをクリックして情報を得るのが一般的でした。ところが現在では、検索結果ページの段階で疑問が解決してしまい、リンク先を訪れないケースが増えています。
- 言葉の定義・説明
- 著名人のプロフィール
- 簡単なノウハウ
たとえば、上記のようなものは検索画面上やAIによる要約表示だけで完結してしまうため、ユーザーが個別サイトを開く必要がなくなってきています。
さらに最近は、生成AIが直接回答を提示する「AI検索」の利用が拡大。生成AIをスマホにアプリとしてインストールして、使用している人も増えています。
ユーザーはAIとのやりとりの中で欲しい情報を得てしまい、企業サイトまで足を運ばないことも珍しくありません。こうした変化は、SEOに依存した集客モデルの限界を浮き彫りにしています。
このような状況に対応するには、回答そのものにブランドを自然に組み込むLLMOが不可欠です。つまり、ユーザーがAIの答えを目にするその瞬間に、自社の存在を認識してもらえる仕組みづくりが求められます。
若い世代の間では、すでにAIの活用は日常生活の中に組み込まれているため、企業もそれに対応しなければなりません。
早期対策によるブランド露出のメリット
生成AIが情報を引用する際、必ずしも全ステークホルダーに均等な露出機会があるわけではありません。AIは学習データや外部参照元の信頼性を基準に、限られた情報だけを回答に採用します。
そのため、引用枠は早い者勝ちの傾向が強く、一度AIに「信頼できる情報源」と認識されると、継続的に回答内で紹介される可能性が高まります。
今はまだ、LLMOに取り組む企業は少数派です。しかし、生成AI検索の普及とともに競争は急速に激化する見込みです。
SEO黎明期に早く着手した企業が長期的な優位を築いたように、今こそ動き出すことで将来のポジションを確保できます。
他の企業がやっているのを様子を見てから、という姿勢では、LLMO対策に着手する際には競合が増え、難易度が高くなっているでしょう。
早期対策の主なメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 競合が少ない今、AI回答内での露出確率が高い
- 一度引用実績ができれば長期的に掲載されやすい
- ブランド名が自然に記憶され、指名検索や問い合わせにつながる
この流れを踏まえると、LLMOは「将来のための準備」ではなく、「今すぐ着手すべき施策」です。
AIが有力な情報収集や判断の経路となる時代で、優位なポジションを取れるかは、この数年の行動で決まります。
株式会社PROBSOLではLLMO対策の無料相談を受け付けておりますので、最新のLLMO対策の動向について学びたいという方はお気軽にご連絡ください。
LLMO対策5選 基本戦略を解説
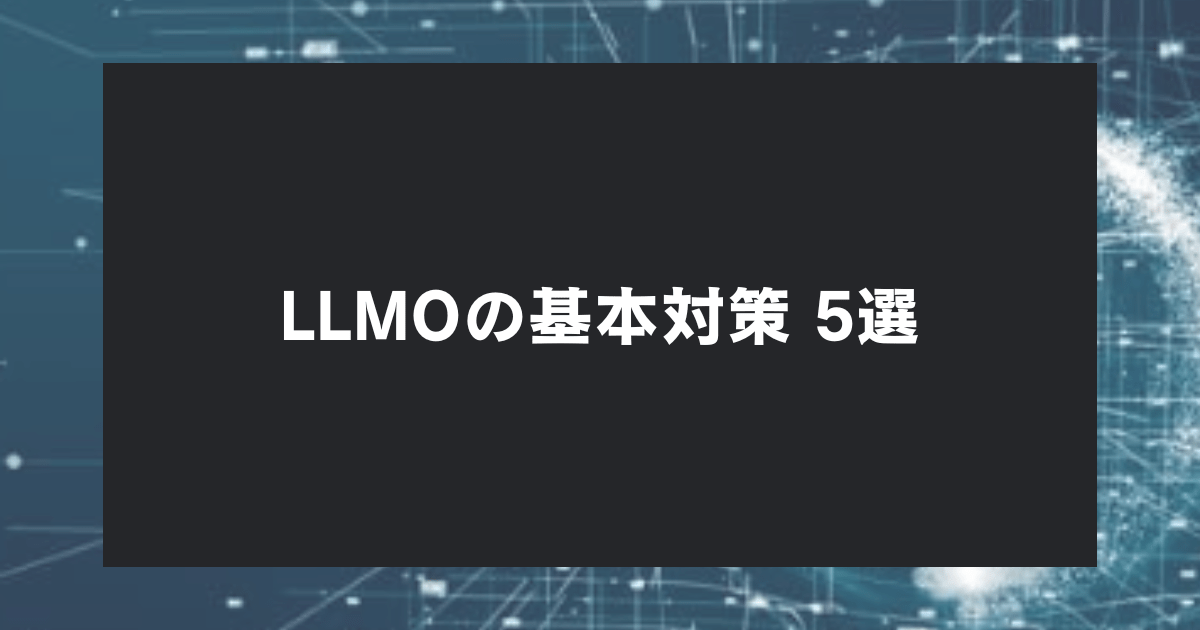
生成AIに自社の情報を正確に理解・引用してもらうためには、単に情報を発信するだけでは不十分で、AIは人間のように文脈を推測するのではなく、機械的に構造や信頼性を判断します。
そのため、AIにとって理解しやすく、誤解しにくい形で情報を設計することが重要に。ここでは、そのための主要戦略を整理していきます。
基本的なLLMO対策に関してはSEO対策と類似することは多く、およその理解としてはSEO対策の延長線上にLLMO対策があるという認識でも問題はありません。
適切な対策が講じられているかどうかを今一度確認して、抜け漏れがないようにしておきましょう。
構造化データの最適化
構造化データとは、コンピュータに文字情報を認識させるためのデータのことで、これによって本来は人間の言葉を理解できないコンピュータがある言葉が持つ意味を認識できます。
例えば、HTMLのタグを使って実装すると、テキストが単なる文字の羅列としてではなく、そのタグに応じた意味や文脈をふまえた文章として捉えられるようになります。
コンピュータが効率よく情報を収集・解釈できるので、質問と回答の対応関係が明確になり、AIの引用精度が高まるのです。
SEOの施策手段のひとつとして「構造化マークアップ」と呼ばれることもあります。
FAQページ・Q&Aコンテンツの整備
FAQはAIにとって非常に扱いやすい情報形態です。質問部分にはユーザーが実際に尋ねそうな自然な言い回しを使い、回答は短く的確にまとめます。
簡単なポイントとしては次のようなことに意識しておくと良いでしょう。
- 1問1答形式を徹底
- 回答は冗長にせず、要点を冒頭に置く
- 構造化マークアップも併用し、機械的な理解度を向上
情報の提示の仕方を変えるだけですが、こうしたFAQは、AI検索やチャット型生成AIの引用にも直結します。
llms.txtの活用(生成AIクローラーへの指示)
AIが情報を引用する仕組みは、事前に取得したコンテンツや最新のクロール情報に依存します。
そのため、このファイルを活用して「ここを見てほしい」「ここは引用しないでほしい」と明示することが、AIにおける情報の正確性や引用率を高める鍵になります。
llms.txt は、生成AIが利用するクローラーに対して、サイト内の情報をどの範囲まで取得・利用してよいかを伝えるための指示ファイルです。
名前の由来は「Large Language Models(LLMs)」+「text file」。検索エンジンのクローラーに対してアクセスルールを定めるrobots.txt に似ていますが、対象は検索エンジンではなく生成AIやAI検索エンジンです。
生成AIは、無差別にすべてのページを同等に扱うわけではありません。取得できるページや情報が制限されていたり、古い情報を参照してしまうこともあります。
もし、自社が強調したい最新データやブランド説明があるのに、AIがそれを拾わず古い記述を使ってしまえば、誤情報や競合優位の損失につながりかねません。
llms.txtを設定することで、AIにとって必要な最新情報へアクセスさせたり、引用してほしくない情報を除外させたりできます。同時に、優先的に見てほしいコンテンツを明示するといった調整も可能になります。
特に短期的な施策として有効で、AIが優先的に参照すべきページを示すことで、重要コンテンツの引用率向上につながるでしょう。
一次情報と高品質コンテンツの発信
生成AIは、信頼できる一次情報や独自性の高いデータを重視します。
引用の土台になるのは、単なるまとめ記事ではなくオリジナルの価値を持つ情報です。
既存の記事を要約しただけの二次情報や、出典が曖昧な情報は、AIから見れば信頼性が低く、引用の優先度も下がります。
一次情報で高品質としてみなされる有効な事例としては、独自の市場調査レポート、専門家の見解、統計データや実験結果など。
また、一次情報に継続的な更新・追加が加えられるとさらに優位性が増します。
- 毎年の市場調査をアップデート
- 季節や四半期ごとの動向レポートを発表
- 新規実験やテスト結果を追記
上記のような定期更新は、「常に新しい一次情報を持つサイト」としてAIに認識されやすくなり、長期的な引用維持につながります。
AI経由で知った情報の出典が明確であれば、そのブランドへの好感度や信頼感は大きく高まるため、この施策はAIのためだけでなく、人間のための情報設計でもあると言えるでしょう。
引用されやすい情報設計にする
生成AIに自社の情報を引用してもらうためには、ただ情報を発信するだけでは不十分。
AIが文章を解析し、他の情報源と比較したうえで引用を決める際には、「理解しやすさ」と「信頼できる根拠」が大きな判断基準となります。
そのため、情報の見せ方・構造そのものを最適化することが重要です。
- 箇条書きで要点を整理し、視認性を高める
- 明確な出典リンクを提示し、信頼性を補強
- 数値や統計データを明示して具体性を持たせる
- 一文で説明できる簡潔な定義を用意する
繰り返しになりますが、これらの工夫はすべて、AIが情報を「機械的に解析しやすい形」に整えることに役立ちます。
文章が整理され、根拠や具体性が付与されているほど、AIはそれを「信頼できる回答素材」と判断しやすくなるでしょう。
その結果として、生成AIが回答文にあなたの情報を盛り込む確率が大幅に向上します。
4ステップで出来る LLMO対策の実践方法
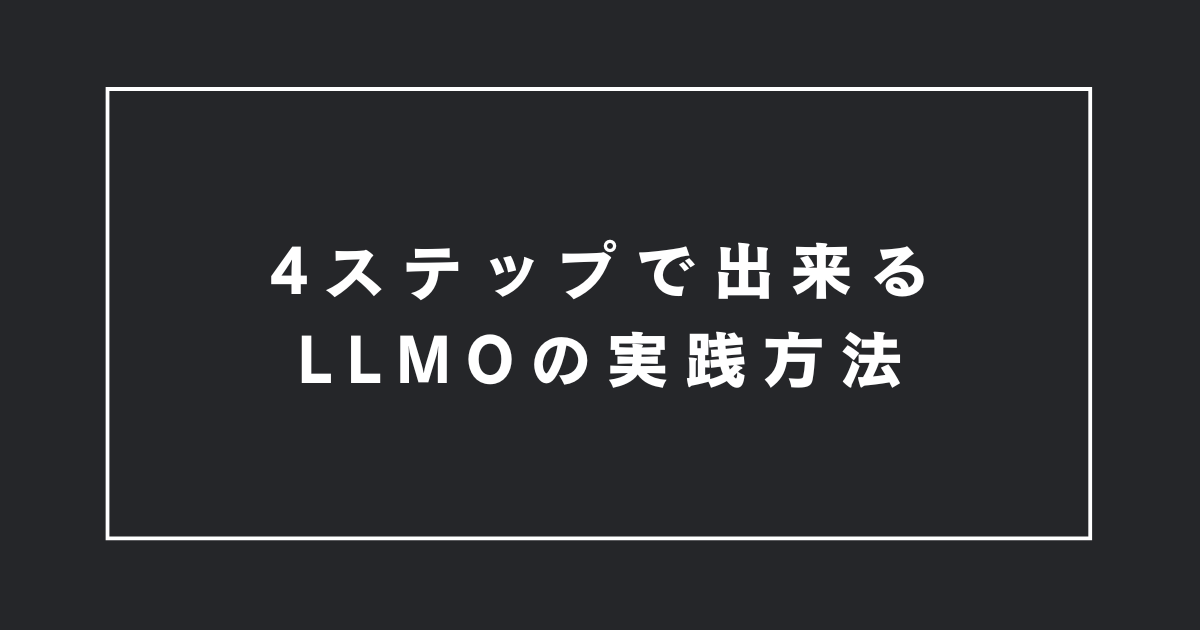
ここまで、基本的なLLMO対策をご紹介してきましたが、LLMOは単発の施策で終わらせるのではなく、現状把握から改善、運用までを一連のプロセスとして進めることで効果を最大化できます。
以下は、実務に落とし込みやすい4つのステップです。
- 自社サイトの現状分析(引用実績の有無を調査)
- 改善の優先順位付け
- 被リンク・権威性の強化施策
- 継続的な検証と改善サイクル
各ステップについて、LLMO対策を進めたいと考えている企業向けに実施すべきことをまとめたので、それぞれ確認していきましょう。
まず最初に行うべきは、「今、自社がAIにどれだけ引用されているのか」を知ること。これにより、後の優先順位付けのステップや目標の策定なども行いやすくなります。
対象となるAIへの質問に関して手動でリサーチを行ったり、ahrefsなどのツールを使用したりすることでデータを取得できます。
この調査は、単なる引用有無の確認だけでなく、AIが自社をどう認識しているのかを把握する意味でも重要です。
引用実績がなかった場合や競合に埋もれている場合は、まず競合が少ないニッチな領域のキーワードから取り組むのがおすすめです。
AIが参照する情報源が限られるため、特定の条件や用途に絞ったほうが自社コンテンツが引用される確率が高まります。
この段階で得られた効果的な施策は、その後の広いキーワード領域への展開にも活用できるでしょう。
また、先述したLLMOの基本的な戦略や短期的な施策に関しては、取り組むコストが比較的小さいので、早めにやっておくことをおすすめします。
- LLMS.txt ファイルを作成→ルートディレクトリに設置
- 構造化マークアップ
- 分かりにくい情報の提示を改善する
- エンティティ関連ページの強化
エンティティとはそれがそのものだと他と区別できる対象のことで、例えば自社のブランドやサービス名について調べた時、そのものが出てくるかどうかで判断できます。
アバウトページや著者ページの整備などがこれにあたります。
生成AIは「情報の正確性」だけでなく「情報源としての権威性」も重視します。
そのため、被リンクとブランドの権威性強化は不可欠。
これらは、時間がかかる場合や費用がかかる場合など、状況によって異なりますが、業界内での優位性を保つには非常に効果的な施策です。
- プレスリリースによるニュース露出
- 公的機関や教育機関からのリンク獲得
- 学会発表やカンファレンス登壇
- 専門書籍やホワイトペーパーの出版
- 業界メディアへの寄稿やインタビュー掲載
商品・サービスに関するユーザーのレビューや第三者の比較記事などの評価の対象となると考えられます。
生成AIの引用基準やアルゴリズムは固定されておらず、時間とともに変化します。
そのため、一度引用されたからといって放置するのは危険です。
- 定期的に引用状況をモニタリング
- 新しい引用元や参照傾向を分析
- 必要に応じてコンテンツや構造化データを更新
- 新しいキーワード領域に拡大
PDCAサイクルを回しながら、「常に最新・正確・信頼できる情報源」であり続けることが、長期的なLLMO成功の鍵です。
細かな施策に関してはそれぞれの企業によって異なるため、最適なLLMO対策が知りたいという方はお気軽にご相談ください。
LLMO対策における注意点と乗り越えるべき課題

LLMOは新しい分野であり、効果を最大化するためには特有の注意点やハードルを理解しておく必要があります。
一般的な企業が自社で取り組む上では、次のような課題に直面することが予想されるでしょう。
- 効果測定の難しさ
- 不正確な引用や意図しない切り取りのリスク
- 技術的・運用的なハードル
まず、最大の課題の一つが効果測定の難しさです。
現時点では、生成AIが自社情報をどの程度引用しているかを自動で集計できる専用ツールは限られており、多くの場合、ChatGPTやPerplexity、Google Geminiなどに直接質問し、回答内容を手動で確認・記録する必要があります。
この作業は時間がかかりますが、定期的な調査が長期的な成果把握には不可欠です。
次に注意すべきは、不正確な引用や意図しない切り取りのリスクです。
生成AIは文脈の解釈を誤ることがあり、意図とは異なる表現や誤情報を含めてしまう場合があります。
これを防ぐためには、文章を簡潔かつ明快にし、定義や数値は曖昧さを避けて記述することが重要。
特に専門用語や固有名詞は説明を添え、誤解の余地を減らす工夫が求められます。
さらに、技術的・運用的なハードルも存在します。
構造化データの最適化やllms.txt の設定、サーバーへのファイル配置など、一定のウェブ技術やマークアップの知識が必要になる場面があります。
自社内でリソースが不足している場合は、外部のSEOやAI最適化に精通した専門家と連携し、効率的かつ確実に実装を進めることが望ましいでしょう。
これらの課題は一見複雑に思えますが、事前に認識し、適切な運用フローを設計すればリスクは最小化できます。
今後の展望と最新動向:AI検索時代に向けた備え

LMOを取り巻く環境は急速に変化しており、主要プレイヤーの動きからもそのスピードがうかがえます。
Googleは「AI Overview」の精度向上を継続し、より文脈に沿った情報提示を目指しており、OpenAIはブラウジング機能を改善し、最新情報をリアルタイムに参照できるよう進化中です。
Microsoftも「Copilot Search」の機能強化を進め、Bing検索とAIアシスタントの融合を加速させています。
各社の競争は、AI検索の品質とユーザー体験を一層引き上げることになるでしょう。
今後のAI技術に関する進化予測としては、音声入力による対話型検索の普及や、画像・動画を含むマルチモーダル検索の拡大が挙げられます。
AIはテキスト情報だけでなく、ビジュアルや音声データも含めて横断的に分析し、最適な引用元を選定するようになると考えられます。
つまり、これからのAI検索は「一つの情報形式」に依存せず、複数のメディアを組み合わせて回答を生成する時代へと進化していくでしょう。
こうした変化の中で、企業や情報発信者には一貫して次のような姿勢が求められます。
- 一次情報の充実
- 権威性の明示
- 情報更新頻度の維持
AIは鮮度の高い信頼情報を優先的に引用するため、古い情報や曖昧な記述は存在感を失っていきます。
ブランド価値を高め、AI検索での露出を維持するためには、正確かつ最新の情報を継続的に発信し、業界内での信頼ポジションを確立しておくことが不可欠です。
LLMO対策に関するよくある質問(FAQ)

最後にLLMO対策に関するよくある質問に関してまとめました。
すでに解説を行った点もありますが、企業担当者が疑問に感じる点を再度まとめたので、LLMO対策に取り組む上での不安を取り除くためにも今一度ご確認ください。
LLMO対策は小規模サイトにも必要ですか?
結論から言えば、小規模サイトであってもLLMO対策は有効であり、むしろ早期に着手することで大きなメリットを得られる可能性があります。
生成AIは、必ずしも大規模サイトや有名ブランドだけを優先して引用するわけではありません。
AIは、情報の独自性・正確性・構造化の度合いを重視するため、小規模サイトでも条件を満たせば十分に引用対象となります。
小規模ゆえの制約は確かにありますが、それを補う特化性や正確さ、更新の頻度の観点などで競争を勝ち抜ける可能性は十分にあります。
SEO対策とLLMO対策はどう使い分ければいいですか?
SEOとLLMOは目的や評価基準が異なるため、補完関係で運用することが重要です。
SEO対策とLLMO対策で共通している施策も存在するため、すでにSEOに取り組んでいる企業はLLMOの視点を追加で取り入れて強化、SEO対策を十分に行っていない場合は、LLMOと共通して重要な施策から取り組んでいくのが良いでしょう。
使い分けの基本は、SEOでアクセスを取り、LLMOで認知を取るという考え方もメディア運用としては分かりやすいと言われています。
効果が出るまでどのくらい時間がかかりますか?
LLMO対策の効果が現れるまでの期間は、サイトの現状や施策内容、競合状況によって大きく変わりますが、目安としては早ければ1〜3か月、平均すると3〜6か月程度です。
短期的に成果が上がることはもちろんありますが、重要なのは「短期で結果を求めすぎない」こと。
むしろ、中長期的な情報発信の一環としてLLMOを組み込み、半年〜1年単位での改善サイクルを継続する姿勢が必要です。
LLMO対策は一度やれば完了しますか?
LLMO対策は、一度の実施で終わる性質のものではありません。理由は大きく3つあります。
- 生成AIの学習データが更新され続けるため
- 引用アルゴリズムが変化するため
- 競合状況が動くため
LLMOは「一度の施策」ではなく「継続的な運用」として捉えることが重要です。
ただし、忘れてはいけないのが、LLMO対策は単なるLLMO対策としてだけ機能するのではなく、ユーザーにとっても有意義なものであるということ。
データの更新やメディアの見直しを行うことは、ユーザーにとって価値のある形で、企業ブランド・サービスを維持し続けるためには必要不可欠なものであると心得ておかなければなりません。
まとめ
最後に、この記事の内容をまとめます。
- LLMOは大規模言語モデル(LLM)に向けた情報最適化の手法
- AI を用いた検索行動の増加により、重要度が高まっている
- 時代の変化に取り残されないためには早期に対応することが大切
ChatGPTやGoogle SGE、Microsoft Copilotなど主要なAI検索サービスが急速に普及する中、企業がデジタルマーケティングで成功を収めるためには、従来のSEO戦略に加えてLLMO対策が不可欠となっています。
LLMO対策は一朝一夕で完成するものではない、しかし、AI検索時代において企業の競争優位を築く上で避けて通れない重要な戦略です。
本記事で紹介した手法を参考に、自社に最適なLLMO戦略を構築し、新しい時代のマーケティングで成功できるようにしましょう。
弊社でも最新の知見を取り入れたLLMO対策の支援を行っています。
LLMOについて関心はあるものの、自社でできるか不安という方はお気軽にご相談ください。
>> LLMO対策のプロに相談してみる